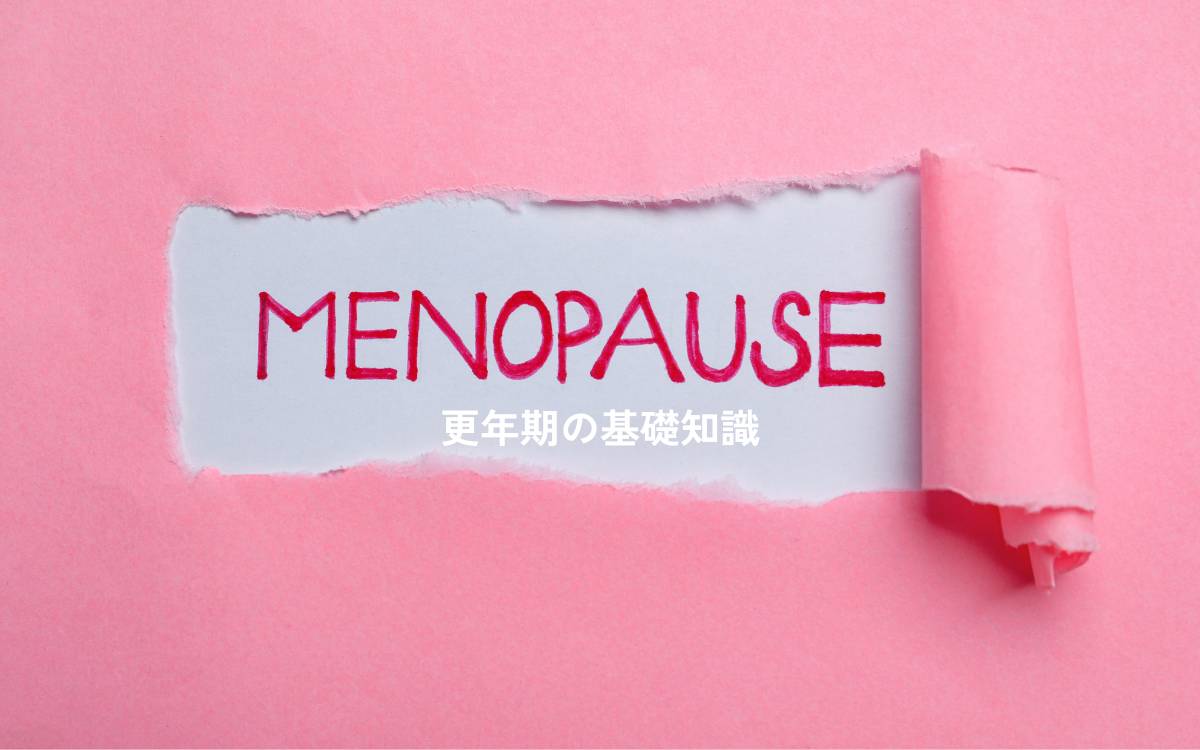閉経や更年期の症状は、誰にでも同じように現れるわけではありません。まったく症状がない人もいれば、日常生活に支障をきたすほどつらい人もいます。ここでは、アメリカで暮らす日本人女性が知っておきたい基本情報と、よくある質問をまとめました。
- 更年期といえば「ホットフラッシュ」などをよく聞きますが、典型的な症状にはどのようなものがあり、平均してどのくらい続くのでしょうか?
-
更年期で最も典型的な症状は「ホットフラッシュ」(急に顔や体が熱くなる症状)や「発汗」です。他にも「不眠」「不安」や「気分の変動」などの精神症状や「関節痛」「泌尿器・膣の症状」などの身体症状があります。更年期症状起こる頻度は個人で大きく異なり、持続期間も人によってさまざまです。
ホットフラッシュは閉経前後に一番起こりやすく、時間が立つと軽減されていきます。アジア系の女性のホットフラッシュの持続期間は比較的短く、平均して5年前後と言われています。「泌尿器・膣の症状」に関しては年とともに低下するエストロゲンによって引き起こされるので、年齢とともに症状は強くなっていきます。
- 「更年期障害」は、英語でなんというのでしょうか?
-
ホルモンの変動が最も大きい閉経前後の時期に起こる症状のことをまとめて Perimenopausal syndrome といいます。
- ホルモン補充療法(HRT:Hormone Replacement Therapy)のメリットとリスクについて、アメリカの医師はどのように説明しているのでしょうか?
-
更年期障害の治療の一つに、ホルモン補充療法(HRT)にはいくつかの方法(飲み薬、パッチの貼り薬やジェル、局所に塗るクリームなど)があり、症状の内容や健康上のリスク、患者さんの希望などによって決めます。
アメリカでは、HRT を始める際にメリットとリスクの両方をきちんと理解した上で、医師と患者が一緒に治療方針を決めるのが一般的です。
私の印象としては、更年期障害による生活の質(Quality of Life:QOL)の低下が考慮されるようになり、これまで以上に患者の意思決定が重視されるようになったと思います。
HRTを使用するメリットとしては、
・特にホットフラッシュや発汗の更年期症状が改善される
・それに伴い、睡眠の質や気分の不調が軽くなる可能性がある
・長期的には、骨粗そう症や将来の骨折のリスクを下げる効果が期待できる。一方で、HRTには副作用やリスクもあるため、必要な効果が得られる最も少ない用量を、できるだけ短い期間だけ使用することが推奨されています。
- アメリカで更年期の相談をしたい場合、まずどこに相談するのでしょうか?かかりつけ医でしょうか?
-
かかりつけ医(プライマリケア・ドクター)に相談してみることをお勧めします。多くの場合、プライマリケア・ドクターが初期対応し、必要があれば専門医を紹介することもできます。
- 更年期に関する治療や薬は、医療保険でどの程度カバーされるのでしょうか?
-
アメリカの保険制度はとても複雑で、それぞれの患者の保険プランによってカバーされる範囲が異なるのが現場です。しかし、更年期障害は本当のmedical conditionなので、他の病気と同じく診察料は医療保険である程度カバーされるはずです。
- 日本では漢方薬を使う方も多いですが、アメリカで入手できるものもありますか?代替療法やサプリメントがそれにあたるのでしょうか?その場合、更年期の症状を和らげる代替療法やサプリメントにはどのようなものがありますか?
-
更年期障害の治療については、まだ十分な研究が行われていません。特に、サプリメントや代替医療といった分野では、科学的な根拠が少ないのが現状です。
一方、ホットフラッシュや寝汗といった更年期によくみられる症状に対しては、効果がしっかりと確認された処方薬があります。そのため、医療現場ではこれらの薬が第一の治療法(ファーストライン)として勧められることが多いです。
ただし、「なるべく薬を使いたくない」という方には、認知行動療法(CBT:Cognitive Behavioral Therapy)という心理療法も選択肢の一つです。専門のカウンセラーによるCBTには、ホットフラッシュや寝汗の頻度を減らし、睡眠の質を改善する効果があるという研究結果があります。
また、サプリメントの中では植物エストロゲン(大豆イソフラボンなど)がもっともよく研究されています。これは弱い女性ホルモン(エストロゲン)に似た働きを持ち、ほてりの回数や膣の乾燥をわずかに軽減する可能性があるとされています。
ただし、市販されているサプリメントは成分や含まれる量に大きなばらつきがあるほか、長期的な安全性がまだ十分に確認されていない点に注意が必要です。使用する際は、医師や専門家に相談することをおすすめします。
- 更年期症状を和らげるために、食事・運動・睡眠といった生活習慣で特に気をつけるべき点はありますか?
-
軽い〜中くらいの更年期症状に対しては、食事や運動などの生活習慣(ライフスタイル)の改善が効果的で、医療の現場でも推奨されています。特に、薬を使いたくない人にとってはおすすめです。
ただし、現時点では「これが正解」というような明確なガイドラインや十分な研究データはまだそろっていません。とはいえ、いくつかの研究から次のような傾向がわかっています。
- 野菜や大豆製品を多くとる
- 鶏肉や脂肪分の多い乳製品を控える
このような食事を心がけることで、ほてりやホットフラッシュ、不安感などの症状が軽くなる可能性があります。逆に、体脂肪率が高いと症状が強くなる傾向があるとされています。
また、定期的に心拍数が上がるような強度の高い運動は、更年期症状の改善に役立つと考えられています。ただし、ホットフラッシュなどをどのくらい減らせるかについては、まだはっきりしたことはわかっていません。
さらに、睡眠の質と時間を改善することもとても重要です。質の良い睡眠は、不眠やほてりなどによる日中の不調を大きく軽減し、気分や生活全体の質(QOL)を高めることがわかっています。
特に効果があるとされているのが、次の3つです。
- 不眠症に対する認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia: CBT-I)
- 適度な運動
- マインドフルネス(心を落ち着けるトレーニング)
特にCBT-Iは長期的な効果が高いとされています。睡眠が改善すると、ホットフラッシュや気分の落ち込みなども軽くなり、生活全体の質が改善します
- 骨粗しょう症や心疾患のリスクが高まると聞きますが、予防や検診はどのように受けるのがよいでしょうか?
-
成人の健康診断は、年に一度、プライマリケア・ドクターのところで受けることが勧められています。その時にどのようなスクリーニングが必要か聞くことをお勧めします。
例えば、一般的に女性の骨粗そう症のスクリーニングは65歳からですが、個々のリスクファクターによって異なることがあるので、直接プライマリケア・ドクターに相談するのが最適です。
- 気分の落ち込みや不安といったメンタル面の不調が出た場合、どこに相談するのが適切でしょうか?
-
これもまずはプライマリケア・ドクターに相談しましょう。多くの場合、プライマリケア・ドクターが更年期にともなう不安や落ち込みに対応することができます。また、カウンセリングや必要があれば、プライマリケア・ドクターから精神科などの専門医も紹介できます。
- 更年期の始まりや閉経の時期には個人差が大きいと聞きますが、一般的には何歳くらいから始まり、どのくらい続くのが平均ですか?人種で違いはありますか?
-
世界的に女性の閉経の平均年齢は51才前後で、ほとんどの女性は45から56才の間に閉経します。閉経というのは、最後の月経から丸12ヶ月がたった時点で「閉経」と定義されます。平均的な更年期の始まりは47.5才で、平均して3.8-6.3年して閉経を迎えます。日本人女性の平均閉経年齢ははこれよりやや遅く、52.1歳と言われています。
- 更年期の症状がひどいのですが、「自分は更年期の症状なんてなかった」という人から理解してもらえず、辛い思いをしています。どのようにしたら個人差があること、中には治療を受けなくてはならないほどの人がいることを理解してもらえるでしょうか?
-
更年期の症状は、女性ホルモンの減少に対する反応であり、ほとんど症状がない人もいれば、ホットフラッシュ、不眠、気分の落ち込み、集中力の低下などで日常生活に支障をきたすほどの人もいます。
実際、調査によると約4〜5割の女性が「治療を検討するほど症状がある」と回答しています。このような数字を伝えることで、いかにたくさんの女性が影響を受けているか、更年期症状を軽く見てはいけないことを理解してもらえるかもしれません。
でも、実際に経験していないと更年期症状のつらさは理解しにくいので、「自分は更年期の症状なんてなかった」と言われてしまうと、理解されないことで更にストレスを感じやすいですね。まずはご自身の体と心を大事にしながら、信頼できる人や医療関係者とつながってください。
このような問題を解決するためには、社会全体で女性の更年期に対する意識の向上が必要だと思います。
- 閉経後の健康管理で、特に重要なポイントは何でしょうか?
-
食事と運動はいつでも大切ですが、特に閉経後に関して気を付けるポイントは次のとおりです。
野菜を中心としたバランスの良い食事を心がけましょう。
カルシウムをしっかりとることが重要です:乳製品・大豆製品・緑黄色野菜・小魚・ナッツなど
たんぱく質も意識してとりましょう:魚・豆製品・肉など。閉経後は女性ホルモン(エストロゲン)の減少により、骨密度が低下しやすく、骨折のリスクが上がります。
食事で十分にカルシウムがとれない場合は、サプリメントで補う方法もあります。ただし、カルシウムのとりすぎは尿路結石などの問題につながることもあるため、プライマリケア・ドクターと相談して目標量を決めるのが安心です。また、閉経後は基礎代謝が下がり、筋肉量も減少しやすくなるため、食事を通してたんぱく質を意識的にとることがより大切になります。
さらに、さまざまな運動を行うことが大切です。
- 有酸素運動(ウォーキングや速歩など)は、心臓や血管の健康に良い影響があります。
- ウォーキングのような重力に逆らう運動は骨を丈夫に保つ効果もあります。
- 週に150分程度の有酸素運動が推奨されています。
- ヨガなどのバランストレーニング、ウエイトトレーニングなどの筋力トレーニングも取り入れると効果的です。
そして、喫煙や飲酒は控えた方が、骨の健康を維持できます。
- 50歳を過ぎた頃から更年期の症状と思われる変化が現れ始め、「これは更年期のせい?」それとも「老化現象なの?」と感じることが増えてきました。以前は何気なくできていたことが、ふとした瞬間に難しく感じられるようになっています。たとえば、上の棚にある重い鍋を軽々と取ることや、立ったまま靴下を履くといった動作が、日によってスムーズにできなかったりします。こうした少しずつ感じる変化は、更年期によるものと考えるべきなのか、それとも老化現象として受け止めるべきなのでしょうか。
-
更年期に経験する「これは更年期?それとも老化?」という変化は、多くの場合、両方の影響が重なっている可能性があります。
ただし、更年期症状はエストロゲンの急激な変化によるものが多く、加齢による緩やかな変化とは異なり、ある日突然気づくケースも少なくありません。
いずれが原因であっても、日常生活に運動を取り入れることで、体力や筋力を維持し、バランス感覚を高めることが可能です。こうした習慣は、更年期症状の軽減や加齢に伴う体の変化への対応に役立ちます。
- 体力や認知面での変化に対して、どのように心の整理をつけ、前向きに対処していけば良いのでしょうか。
-
更年期や加齢によって体力や認知面に変化を感じると、つい「できなくなった」「変わってしまった」とネガティブに捉えがちです。
でも、こうした変化は多くの人が経験する自然なライフステージの一部と考えることで、前向きな視点を持ちやすくなるかもしれません。
これまで続けてきたことが合わなくなったと感じるときは、少しずつ自分のリズムを調整したり、新しいことに挑戦してみるチャンスでもあります。小さな変化が、新たな発見や出会いにつながることもあるでしょう。
その時々の年齢やライフステージに合わせて、自分なりのバランスを見つけることが大切だと思います。
執筆:西連寺智子先生(さいれんじ・ともこ)
University of Washington Department of Family Medicine, Associate Professor
Family doctor at UW Primary Care at Northgate Clinic and Northwest Hospital
米国マサチューセッツ州で幼少時代を過ごし、12歳で日本に帰国。国際基督大学卒業後、岡山大学に学士編入。卒業後、福岡県にある飯塚病院での2年間にわたる初期研修を経て、ピッツバーグ大学メディカルセンターで家庭医のレジデンシーとチーフレジデントを行う。同大学で医学教育修士課程とファカルティデベロップメントフェローシップを終え、現在はワシントン大学医学部(University of Washingon School of Medicine)で家庭医療の准教授として医学生の指導を行いながら、UW Medicine のノースゲート・クリニックと Northwest Hospital で家庭医として勤務している。
当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や医療アドバイスではありません。読者個人の具体的な状況に関するご質問は、直接ご相談ください。